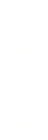月別アーカイブ: 2025年7月
YOSAPARK Rankaのよもやま話~第12回~
皆さんこんにちは!
宮崎県都城市でリラクゼーションサロン・妊活・マタニティケア・ボディケアを行っている
YOSAPARK Ranka、更新担当の富山です。
温活の鉄則とは?~“ただ温める”だけじゃない!体と心を整える5つのルール~
今回は、温活を日常生活で実践する上での**「鉄則」**をご紹介します。
「とにかく体を温めればいいんでしょ?」――
確かにそれも正解ですが、実は温活には効果的なやり方と、注意すべきポイントがいくつもあります。
体質や生活習慣に合わせた“正しい温活”で、日々のコンディションをぐっと底上げしていきましょう!
■ 鉄則①「温めるべき“3つの首”を意識する」
温活の基本中の基本。それは、「首・手首・足首」の3つの“首”を冷やさないこと。
この3ヶ所は、血管が皮膚に近く、冷えると一気に全身の体温が下がるといわれています。
逆に、ここを温めることで、効率よく体の芯からポカポカしてくるのです。
実践例:
-
スカーフやネックウォーマー
-
リストバンドや手袋
-
レッグウォーマーや足首カバー
“おしゃれ”と“温活”の両立も、意識次第でできますよ!
■ 鉄則②「内側から温める食事をとる」
体は食べたものでできている――それは温活でも同じです。
「温かい食事をとれば良い」と思いがちですが、実は食材の“性質”がカギを握っています。
体を温める食材(一例):
-
生姜、ねぎ、にんじん、ごぼう、かぼちゃ
-
玄米、味噌、黒豆
-
シナモン、クローブ、唐辛子(適量)
温かいスープやお味噌汁をベースに、これらの食材を積極的に取り入れていきましょう。
冷たい飲み物や生野菜の過剰摂取は、内臓を冷やす原因にもなるので注意です。
■ 鉄則③「“温めすぎない”ことも重要」
実は温活で見落とされがちなのが、「温めすぎ」への注意です。
サウナや電気毛布などで外部から強く熱を加えすぎると、体が“熱を逃がそう”として逆に冷えを招くこともあります。
大切なのは、体が自ら温まる力=基礎体温を高めること。
-
適度な運動(ウォーキングやストレッチ)
-
入浴は38〜40℃のぬるま湯でゆっくり
-
暖房に頼りすぎず、自律神経を整える
“やりすぎない温活”が、長続きのコツです。
■ 鉄則④「冷えの原因は生活習慣にある」
単に気温が低いから冷えるのではなく、冷えを引き起こす習慣やストレスも見直すことが重要です。
-
睡眠不足 → 自律神経の乱れ
-
運動不足 → 筋力低下・血流不良
-
スマホの使いすぎ → 首こり・末端冷え
-
緊張・ストレス → 末梢血管の収縮
これらを放置していては、どんなに外側から温めても“根本解決”にはなりません。
温活とは、生活を整えることそのものでもあるのです。
■ 鉄則⑤「続けることが最大の近道」
温活は“今日だけ”“1回だけ”では意味がありません。
毎日少しずつでも続けることで、体が変わり、調子が安定していきます。
-
朝の白湯を1杯
-
通勤でひと駅分歩く
-
湯船に10分浸かる
-
寝る前の足湯を習慣に
どれも簡単で、お金もかかりません。
「意識すること」から始めて、「無理なく続ける」こと――これが温活成功のカギです。
最後に…
温活は、私たちの体が本来持つ「整える力・守る力・癒す力」を引き出す知恵です。
歴史ある知見と現代的なライフスタイルの融合で、**無理せず心地よく“温まる暮らし”**を、今日から一歩ずつ始めてみませんか?
次回もお楽しみに!
宮崎県都城市でリラクゼーションサロン・妊活・マタニティケア・ボディケアを行っております。
お気軽にお問い合わせください。
![]()
YOSAPARK Rankaのよもやま話~第11回~
皆さんこんにちは!
宮崎県都城市でリラクゼーションサロン・妊活・マタニティケア・ボディケアを行っている
YOSAPARK Ranka、更新担当の富山です。
温活の歴史について〜体を温めることは、いつの時代も人を救ってきた~
今回は、「温活(おんかつ)」の歴史について深掘りしていきます。
今でこそ「温活」は女性誌や健康メディアで頻繁に取り上げられるようになり、日常的なセルフケアとして定着しつつありますが、実はこの“体を温める”という行為には、古代から続く深い知恵と文化が根づいています。
■ 古代から続く「温める文化」
「体を冷やすことは、万病のもと」――この考え方は、何千年も前から世界中に存在していました。
● 東洋医学と温めの原点
中国では紀元前の時代から、冷えは“陽気の不足”とされ、体のエネルギー(気)や血の巡りが悪くなることによって病気を引き起こすと考えられてきました。
漢方では「冷えは未病(病気の手前)」と捉えられ、体を温めるための食材、薬草、入浴法などが体系化されました。
たとえば:
-
生姜やシナモンなどの体を温める食材
-
ヨモギやニンジンを使った温補の漢方薬
-
足湯、薬湯、温石(あたたかい石)を使った治療法
● 日本の「お風呂文化」も温活の一種
奈良時代の仏教文化にもとづく“薬草湯”や“湯治”は、体を温めるだけでなく、心を鎮めるものとしても大切にされてきました。
江戸時代には「銭湯」が庶民の間で広まり、入浴が日常習慣になることで、「温めて癒す」という文化が生活に根づいたのです。
■ 近代における温活の再評価
明治以降、西洋医学が主流になると、体温や血圧、数値による健康管理が重視されるようになりますが、一方で「冷え性」という症状の悩みが顕在化。
特に女性に多く見られる冷え性や生理不順、不眠、慢性疲労などの不定愁訴が社会課題となり、「冷え」が病気の引き金であるという考えが再び注目され始めます。
2000年代以降になると、「温活」という言葉が使われ始めました。
以下のような流れで一般層へと広がっていきます:
-
美容・健康系メディアでの特集
-
エステやリラクゼーション業界の参入
-
冷え性対策商品(腹巻、温感ジェル、入浴剤)の普及
-
スマートフォンによる睡眠・体温管理の普及
つまり、「温めることで整える」「冷えを防ぐことで健康を守る」という東洋的な知恵が、現代的なライフスタイルに合わせて再発見されてきたのです。
■ 温活は“予防医療”の入り口でもある
現代では、生活習慣病やメンタルヘルスの不調が増えるなか、体を温めることが全身の巡りを良くし、自然治癒力を高めるというシンプルなアプローチが注目されています。
冷えにより:
-
自律神経が乱れる
-
血流が悪くなる
-
代謝が落ちる
-
免疫力が低下する
このような連鎖が起こるため、冷え対策=健康維持の第一歩なのです。
温活は、単なる美容やダイエットだけでなく、**「生きる力を育てる生活習慣」**として、これからますます広がっていくでしょう。
次回もお楽しみに!
宮崎県都城市でリラクゼーションサロン・妊活・マタニティケア・ボディケアを行っております。
お気軽にお問い合わせください。
![]()